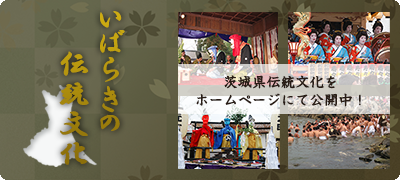つくばからの映像文化の発信を目的とする、10分以内の短編映画のためのコンペティションの「つくばショートムービーコンペティション」。
応募作品144作から2段階の審査を経て最終審査にノミネートされた作品(10作前後予定)を上映します。同時に行われる最終審査会と市民審査員による投票によって各受賞作が決定し、授賞式が行われます。
また、審査員長・中村義洋監督とグランプリ受賞者とのトークセッションも実施します。
※最終ノミネート作品の公表は2月上旬を予定しています。
【審査員長】中村義洋(映画監督/つくば市出身)
【審 査 員】五十嵐立青(つくば市長)
山田健太(株式会社ウィットスタジオ)
中原徹(公益財団法人つくば科学万博記念財団理事長)
つくば観光大使
東京藝術大学に所属するプロフェッショナル・オーケストラである「藝大フィルハーモニア管弦楽団」。本演奏会は、取手市制55周年記念事業として開催されます。
指揮:山下一史
演奏:藝大フィルハーモニア管弦楽団
エコール・ド・パリを代表する画家・藤田嗣治(ふじた・つぐはる/1886-1968)。本展は、藤田の絵画について「写真」という切り口によって再考する世界初の展覧会です。「撮る藤田」、そして「撮られる藤田」にも注目しながら、藤田の絵画と写真の深い関係性についてひもときます。
明治維新までの史料(古文書・記録など)を研究する機関である東京大学史料編纂所。茨城県立歴史館との初の共催で開催する本展は、「島津家文書」(国宝)などの所蔵史料の展示に加え、その仕事や役割について、最近の新たな動きも交え前期と後期にわけて紹介します。
令和8年度開催予定の「ダンス・チャンピオンシップ THE IBARAKI」に向けたプレイベントとして、県内の中学生・高校生を対象に「DANCE SHOWCASE in IBARAKI 2026」を実施します。出場校の日頃の活動成果をぜひご覧ください。
エコール・ド・パリを代表する画家・藤田嗣治(1886-1968)。映像時代を生きた藤田はカメラを愛用し、絵画制作にも活用しました。企画展「藤田嗣治 絵画と写真」(会期:2/10~4/12/会場:茨城県近代美術館)の見どころとともに、藤田の表現について、写真との関係を中心に紐解きます。
講師:澤渡麻里 (茨城県近代美術館首席学芸員)
クラシックギター奏者として長年にわたり第一線で多くの聴衆を魅了し続け、2024年にデビュー55周年を迎えた現在も精力的な演奏活動を展開している荘村清志。公私ともに深い関わりがあった日本を代表する作曲家・武満徹(1930-1996)の作品を取り上げる、没後30年の記念コンサートです。
新版画における代表的な風景画の絵師・川瀬巴水(1883~1957)は、昭和4年に茨城の水郷地域に滞在し牛堀や潮来をテーマにした作品を制作しました。太平洋戦争中には疎開先の栃木から訪れ茨城各地の風景をスケッチしています。戦後には開校したばかりの茨城キリスト教学園を描くためにもたびたび茨城を訪れました。本展の前期は巴水が描いた茨城の風景の新版画と茨城キリスト教大学所蔵の水彩画を、後期は水郷地域の水辺の風景を描いた新版画を展示します。
作品に描かれた女性たちのファッションは、社会的背景や文化を反映し、時代の変遷を雄弁に物語ります。モデルたちの人柄や人生をも伝える重要な役割を果たしていると言えるでしょう。華やかな衣装に身を包む人形たちもまた、作家たちの心を捉えました。本展覧会では、絵画を中心に、画家、児玉幸雄のフランスやドイツで制作されたアンティークドールコレクションや、小説家、柴田錬三郎の日本人形コレクションなどを展示します。
◎同時開催 大島藤倉学園アール・ブリュット展Ⅰ
専門的な美術教育を受けていない人が、美術潮流に流されず、自らの衝動に従って制作するアート「アール・ブリュット」大島藤倉学園の障害をもつ方々による、「リサイクル」をテーマにした作品を、Ⅰ・Ⅱ期に分けて紹介します。
東海ステーションギャラリーでは村内中学生、県内在住・在学の高校生以上の学生を対象に、活動発表の場を提供する一環として施設の開放を行っています。
今展は油彩画を中心に、水彩画やデッサン作品の他、部員が一丸となって取り組んだ共同制作作品も展示します。日頃の活動の成果をご覧ください。
オーストラリアの先住民族の伝統楽器ディジュリドゥ奏者として世界的に評価されているGOMA。2009年、交通事故により脳に大きなダメージを負い、以降、高次脳機能障害の症状に悩まされながら、細かい点描で画面を埋め尽くした独特の絵画を描くようになりました。彼の描く世界は、意識を喪失してから回復するまでに見えるひかりの景色を表しています。不思議でありながら、どこかで出会ったことのあるような、私たちの体の奥底に眠る「ひかりの世界」を体感してください。
体験プログラム「日本画ってなぁに?」では日本画の絵具や用具等について実物を用
いて紹介します。また、横山大観(1868-1958)の「生々流転」(1923)複製画(原本は東
京国立近代美術館蔵、重要文化財)全長約40 メートルを一挙公開します。その他、掛
軸や絵巻の複製を使って扱い方を体験するコーナーや、墨や金色の絵具で描く実技の
体験ができるコーナーもあり様々な角度から日本画に親しんでいただけます。
体験は無料です。
茨城県ゆかりのアーティストによる特別編成タンゴバンド、始動!
魅力的なタンゴの名曲を中心に、出演者によるオリジナル編曲や自作曲も披露。従来のタンゴバンド編成に和の響きを持つ箏・十七絃を取り入れた、唯一無二のサウンドでお届けします。ラテン音楽の歴史や楽器、演奏曲の紹介などのトークとともに、アルゼンチンと日本、レトロとモダンが交錯するステージをお楽しみください。
茨城県では、茨城県美術展覧会(会長:能島征二)と協力し、第14回現代茨城作家美術展(現美展)を開催しています。本展では、日本画、洋画、彫刻、工芸美術、書、写真、デザインの7部門の作品を会派の垣根を超えて展示します。茨城県ゆかりの作家の大作、新進気鋭の若手作家の作品が展示され、なかでも、日本芸術界の最高権威である日本藝術院会員の作品は必見です。
また、関連企画として「出品作家によるギャラリートーク」をはじめ、様々なイベントも開催します。
水戸市出身のピアニスト・古橋明香里と公益財団法人水戸市芸術振興財団(水戸芸術館)が共催で行うコンサート。コンセプトは「クラシックコンサートに馴染みのない方でも気軽に行ける」コンサートで、誰もが耳にしたことのあるクラシック有名曲を中心にプログラムされています。
【プログラム】
ドビュッシー:ベルガマスク組曲より「月の光」
J. S. バッハ:主よ、人の望みの喜びよ
モーツァルト:きらきら星変奏曲 K. 265 (300e)
ショパン:ノクターン 第20番「遺作」
ショパン:華麗なる大円舞曲
リスト:愛の夢 第3番
リスト:ラ・カンパネラ
ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ 第24番 嬰へ長調 作品78「テレーゼ」
ラフマニノフ:楽興の時 作品16 ほか
国内外で活躍する水戸室内管弦楽団の名手たちが茨城県の吹奏楽団や管楽器アンサンブルを指導する公開レッスン。今回は県西地域から受講団体を募集し、茨城県立古河第三高等学校吹奏楽部と茨城県立坂東清風高等学校吹奏楽部が受講します。レッスンを通して音楽が練り上げられていくプロセスには、合奏の奥深さと楽しさが詰まっています。さらに講師たちのアンサンブルによるミニコンサートもございます。
【講師】
岩佐和弘(フルート)
山本正治(クラリネット)
小山弦太郎(サクソフォン)
猶井正幸(ホルン)
若林万里子(トランペット)
小田桐寛之(トロンボーン)
望月岳彦(打楽器)
笠間市を拠点に活動し、表情豊かないきものなど独自の造形表現が魅力の陶芸作家・田崎太郎(1970-)の作品展です。猫神さまなどの神獣から、空を夢見るペンギン博士の飛行機械まで、新作を含む40点を超える作品を通して、その独自の造形と物語の軌跡をたどります。
「近現代日本陶芸の展開」を茨城県陶芸美術館のコレクションを通して紹介しています。
今回のコレクション展II・IIIでは、「磁器の100年」をテーマに、うつわからオブジェまで様々な作品を通して磁器作品の奥深さをお楽しみください。
また、茨城県の作家については、文化勲章受章者の板谷波山や「練上手」の重要無形文化財保持者(人間国宝)の松井康成をはじめ、現在、笠間や県内を拠点に活動する作家も含めて幅広く紹介します。
茨城県では、茨城県美術展覧会(会長:能島征二)と協力し、茨城県移動展覧会「茨城の美術セレクション」を主催しています。
県民の皆様が身近な美術館で芸術を鑑賞できる機会を提供するために、平成28年度より始まったこの移動展覧会は、今年度で10回目を迎えます。
茨城県を代表する芸術家の力作をぜひご覧ください。
昨年度好評を博した音楽講座を今年度も開講します。昭和音楽大学の現役の教授・講師陣による「講義」と、確かな実力を誇り各種公演で活躍中の奏者による「生演奏」でお贈りします。
【第1回】 2025年5月25日(日)
「持ち声を活かす発声講座~かけがえのない“個”が輝くために~」
講師・演奏:上杉清仁(昭和音楽大学講師/カウンターテナー)
演奏:深海侑希(昭和音楽大学伴奏研究員)
【第2回】 2025年8月31日(日)
「“知っているようで知らない”ショパンの魅力」
講師・演奏:川染雅嗣(昭和音楽大学客員教授/ピアノ)
共演:田中浩介(チェロ/昭和音楽大学附属音楽・バレエ教室講師)
【第3回】 2025年12月14日(日)
「音楽で心と脳を活性化!~認知症・介護予防のための音楽療法ワークショップ~」
講師:伊志嶺理沙(昭和音楽大学講師)
演奏:黄木透(テノール/藤原歌劇団団員・日本オペラ協会会員)
辻喜久栄(ピアノ/昭和音楽大学附属音楽・バレエ教室講師)
【第4回】 2026年2月8日(日)
「古楽器と現代楽器の聴き比べ-J.S.バッハ バロック時代の無伴奏チェロ-」
講師・演奏:島根朋史(昭和音楽大学講師/チェロ)
【第5回】 2026年3月29日(日)
「シュトラウス2世のウインナー・ワルツの数々の名作を」
講師:米田かおり(昭和音楽大学講師/音楽学)
演奏:調整中