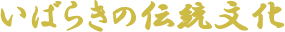関本神社太太神楽
関本神社に古くから伝わる神楽舞である。「高千穂系神楽」に属し正しくは太太御神楽といい、世々相継ぎ絶えることなく永く奉納されるという意味で「代代神楽」に通ずると伝えられている。この神楽は12神楽といわれ、最初は奉幣行事で神楽を行うものすべて参加し、神楽の曲に合わせて大玉串をあげる。第一座は五行の舞、第二座は那岐、那美の舞、第三座は猿田彦の舞、第四座は翁義の舞、第五座は八幡舞、第六座は姪子の舞、第七座は連の舞、第八座は岩戸ひらきの舞と8つの座からなり、笛、太鼓、舞の三要素で構成されている舞楽である。祭礼は毎年3月3日・11月23日に境内の神楽殿にて一般公開されている。[茨城県教育委員会編1996『茨城県の民俗芸能-茨城県民俗芸能緊急調査報告書-』の記載内容をもとに、筑西市の協力を得て、直近の活動実態に近い情報となるよう開催日情報を補足した。]
| 読み仮名 | せきもとじんじゃだいだいかぐら |
|---|---|
| 市町村名 | 筑西市 |
| 活動実施場所 | 関本上(関本神社神楽殿) |
| ジャンル | 神楽 |
| 行事日 | 3月3日・11月23日 |
| 季節 | 春, 秋 |
| 文化財の体系 | 無形民俗文化財 |
| 文化財等の指定区分 | 市町村指定 |
| 指定年月日 | 1975年4月24日 |
| 発祥時期 | 江戸時代(享保年間頃) |
| 存続状況 | 活動中 |
| 活動団体名 | 関本神社太太神楽保存会 |
| 備考 | 写真提供者:筑西市 |