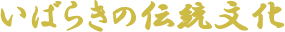潮来節
潮来出島のまこもの中に、あやめ咲くとはしほらしや。潮来出島のまこもの中に、あやめ咲くとはつゆしらず。潮来節は常陸国の潮来村から起こり、江戸時代後期に全国的に歌われた俗謡で、この2首がその元歌であるとするのが通説です。起源は、利根川の船頭唄。あるいは遊女の「梓の唄」であったものが、しだいに花柳界に入ってお座敷唄に変質し、終いには流行歌となって全国的にひろまり、『利根川図志』に見える潮来竹枝の元祖といわれる服部南郭や十返舎一九・小林一茶などの作品に「潮来」や「いたこ」とあるのは潮来節の代名詞で、地名は「板久」と書いて区別しており、「いたこをやらかす」といえば潮来節を歌うことでした。それが全国各地の盆踊りや田植え歌などにとりいれられて、近年まで残っています。潮来節より派生したもの。徳島阿波おどり(よしこの節)、潮来節(親節)、愛媛伊予いたこ節、愛知神戸節、よしこの節、新潟板子、越後いたこ、佐渡おけさ、鳥取嫁入いたこ、本調子いたこ、富山嫁入いたこ、東京深川いたこ、吉原いたこ、品川いたこ都々逸、潮来出島(長唄藤娘)など。(潮来市公式ホームページより)
| 読み仮名 | いたこぶし |
|---|---|
| 市町村名 | 潮来市 |
| ジャンル | 音楽 |
| 文化財の体系 | 無形民俗文化財 |
| 文化財等の指定区分 | 市町村指定 |
| 指定年月日 | 1969年12月13日 |
| 発祥時期 | 江戸時代 |
| 存続状況 | 存続状況不明 |
| 備考 | 写真提供者:潮来市観光商工課 |