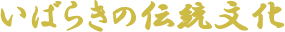根小屋七代天神社代々十二神楽(じゃがもこじゃん)
現在、祝日の11月3日に根小屋に鎮座する七代天神社で代々神楽を奉納する。永禄年間(1558~1570)片野城主の太田(おおた)資正(すけまさ)が久慈郡佐竹郷(常陸太田市)天神林に鎮座する七代天神の神霊を迎え、そのとき代々神楽を奉納したことに始まると伝えられている。代々神楽は午前10時から午後4時頃まで演じられる。以前は林地区のマチ(祭日)である11月8日に行われていた。代々神楽は十二種の舞1槍の舞 2長刀の舞 3剣の舞 4豆撒の舞 5神酒の舞 6田耕の舞 7種蒔の舞 8鬼追出の舞 9餅撒の舞 ⑩鯛釣の舞 ⑪岩剥しの舞 ⑫鞨鼓の舞から構成されている(十二座神楽ともいう)。六座目の田耕の舞での神楽拍子が「ジャガモコジャン」と聞こえるところから、地元では代々神楽を「じゃかもこじゃん」と呼んでいる。六座目の田耕の舞、九座目の餅撒の舞では、境内に向かって餅を撒く場面がある。撒き餅の場面になると、餅を拾う見物人たちで大変にぎやかになる。神楽が演じられる前に、小学生の女の子2人によって巫女舞が奉納される。また、十二座目の鞨鼓の舞でも2人の巫女が四方を固めながら舞う。地元では花舞と呼んでいる。代々神楽は、代々この地で長男に生まれた者に引き継がれたことからその名がついたといわれている。[出典:茨城県教育委員会編2010『茨城県の祭り・行事-茨城県祭り・行事調査報告書』]
| 読み仮名 | ねごやしちだいてんじんじゃだいだいじゅうにかぐら |
|---|---|
| 市町村名 | 石岡市 |
| 活動実施場所 | 根小屋 |
| ジャンル | 神楽 |
| 行事日 | 11月3日 |
| 季節 | 秋 |
| 文化財の体系 | 無形民俗文化財 |
| 文化財等の指定区分 | 市町村指定 |
| 指定年月日 | 1972年12月22日 |
| 存続状況 | 活動中 |
| 備考 | 写真提供者:石岡市教育委員会文化振興課 |