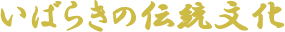天神ばやし
天神ばやしは、天承元年(1131年)に佐竹藩初代藩主佐竹昌義が京より下向し、その2年後に馬坂城主となった頃から秋田へ国替えとなった慶長七年(1602年)まで、城下で農兵を集める際や出陣のときに打ち鳴らされた太鼓が起源と言われます。その後、それが農民の娯楽となり、代々継承され、現在では市の貴重な文化遺産となっています。小太鼓は2/4拍子で素朴そのものですが、それに合わせて打つ大太鼓は、全身の力を振り絞り、最短と強弱を巧みに織り交ぜてのバチさばきで、勇壮果敢で躍動感にあふれ、佐竹藩初期の農民の無骨な気性をよく表現した音曲です。天神ばやし保存会は、昭和52年に結成され、茨城の太鼓演奏会や太田まつり、常陸太田芸能祭などの県内外の各種イベントに多数参加しています。また、保育園や老人ホームでの演奏、小学校や子供会における指導等、伝統芸能の継承にも積極的に取り組んでいます。[出典:「第30回茨城の太鼓演奏会」パンフレット]
ファイルサイズ:685.2MB
| 読み仮名 | てんじんばやし |
|---|---|
| 市町村名 | 常陸太田市 |
| 活動実施場所 | 常陸太田市街地ほか |
| ジャンル | 音楽 |
| 行事日 | 10~11月 他 |
| 季節 | 不定期 |
| 発祥時期 | 天承元年(1131年) |
| 存続状況 | 活動中 |
| 活動団体名 | 天神ばやし保存会 |
| 備考 | 写真提供:天神ばやし保存会 |