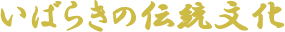柿岡八幡神社太々神楽(じゃがもこじゃん)
毎年旧暦8月15日(十五夜)とその前日に柿岡荒宿に鎮座する八幡神社で太々神楽を奉納する。文禄4年(1595)柿岡城主の長倉(ながくら)義輿(よしおき)が八幡神社を建立した折、伊勢皇大神宮の二十四神楽のうち十二神楽を持ち帰り奉納したという。現在、太々神楽は午後6時から11時頃まで演じられる。以前は一晩中行われていたという。十五夜ということで、美しい月を観賞しながら演じられる太々神楽であるが、神楽が始まると不思議に雨が降るので、いつのまにか「雨乞いの神楽」といわれるようになった。太々神楽は十二種の舞1国堅(くにがため)の舞 2老翁(おきな)の舞 3天狐種嫁(てんこたねがし)の舞 4龍神(りゅうじん)の舞 5赤鬼・地法(あかおに・ちのり)の舞 6神酒(みき)の舞 7西の宮大神の舞 8鈿女(うずめ)の舞 9岩戸(いわと)の舞 ⑩天照大神・戸隠の舞⑪猿田彦大神の舞 ⑫山の神の舞から構成されている(十二座神楽ともいう)二座目の老翁の舞と五座目の赤鬼・地法の舞での神楽拍子が「ジャガモコジャン」と聞こえるところから、地元では太々神楽を「じゃかもこじゃん」と呼んでいる。五座目の赤鬼・地法の舞、十二座目の山の神の舞では境内に向かって餅を撒く場面がある。撒き餅の場面になると、餅を拾う見物人たちで大変にぎやかになる。太々神楽の間に巫女舞が奉納される。「幣の舞」の後、「榊の舞」の後、「扇の舞」の後に9歳から12歳までの柿岡地区から選ばれた小学生の女の子4人によって行われる。現在、太々神楽は八幡町(荒宿、西町、上宿、仲町)の在住者だけが保存会員となっている。[出典:茨城県教育委員会編2010『茨城県の祭り・行事-茨城県祭り・行事調査報告書』]
| 読み仮名 | かきおかはちまんじんじゃだいだいかくら |
|---|---|
| 市町村名 | 石岡市 |
| 活動実施場所 | 柿岡荒宿 |
| ジャンル | 神楽 |
| 行事日 | 十五夜前日夜・当日夜 |
| 季節 | 秋 |
| 文化財の体系 | 無形民俗文化財 |
| 文化財等の指定区分 | 市町村指定 |
| 指定年月日 | 1971年11月26日 |
| 存続状況 | 活動中 |
| 備考 | 写真提供者:常陽藝文センター |