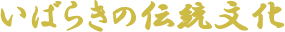太々神楽
江戸時代には3月中旬に2日間太々神楽が奉納された。(古から伝わる田楽、猿楽の舞で祠宮や祝子(はふりこ)が面をかぶって舞ったり笠を持って舞う「はなみおどり」などが大規模に舞われた)。現在では神主が祝詞をあげたあと神宮による笛・太鼓(二つ)にあわせて巫女舞が奉納される(面は保管されているが使用しない)。注連揚舞(しめあげまい)(3人舞)右手に鈴、左手に五色幣を持ち二人で舞う。(大人の巫女)・平舞(4人で舞う)右手に鈴、左手に中啓(扇の形で開かないもの)を持って舞う。明神町など近くの小学生(女子)が4人1組で舞う。1日3回。大漁、豊作祈願。[出典:茨城県教育委員会編2010『茨城県の祭り・行事-茨城県祭り・行事調査報告書』]
| 読み仮名 | だいだいかぐら |
|---|---|
| 市町村名 | 大洗町 |
| 活動実施場所 | 磯浜町・大洗磯前神社 |
| ジャンル | 神楽 |
| 行事日 | 4月 |
| 季節 | 春 |
| 発祥時期 | 少なくとも江戸時代に遡る |
| 存続状況 | 活動中 |
| 活動団体名 | 大洗磯前神社 |